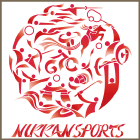開会式で赤いブレザーを着用した日本選手団の行進は、1964年東京五輪の象徴的シーンとして日本人の記憶に刻まれている。デザインしたのは東京で洋服店を経営していた望月靖之さん(故人)。「男に赤はふさわしくない」といわれた時代に、「赤こそ日本の色」と製作に情熱を注ぎ、苦難を乗り越えて夢を実現させた。当時の資料と、五輪公式服装の研究に取り組んできた服飾史家の安城寿子さん(39)の調査研究をもとに、「日の丸カラー」誕生の知られざる秘話をひもとく。【取材・構成=首藤正徳】

- 富士川町スポーツミュージアムに飾ってある望月靖之氏の写真パネル
服飾史家 安城寿子さん調査研究
「男子は真っ赤なブレザー、女子も真っ赤なブレザー(中略)赤と白のコントラストは開催国日本の意志と力を振りまくようであります─」
64年10月10日の東京五輪開会式。入場行進の一番最後に日本選手団が姿を見せたときの、NHKの北出清五郎アナウンサーの実況である。鮮やかな赤はこれまで入場したどの国よりも際立っていた。旗手の持つ日の丸とも相まって、まさしく日本を象徴する色のように映った。開会式はカラー映像でも放送されたことから、鮮烈に日本人の記憶に刻まれることになる。
国立競技場の観客席にいた望月は、後に自伝「ペダルを踏んだタイヤの跡」でこう振り返っている。
「待ちに待ったこの日この瞬間、私はいつ死んでもいい、自分がデザインし、作ったこのブレザーが万雷の拍手を得て、スポーツ界にご奉仕できたのだ」
コメントから心の高ぶりを抑え切れない興奮がうかがえる。無理もない。実に十余年に及ぶ苦難の末に、自国開催の五輪という最高の舞台で夢が実現したのだ。大観衆の拍手も、自分への称賛に聞こえていたのかも知れない。
秩父宮様の言葉が原点に
望月は東京五輪の3大会前、日本が戦後初参加した52年ヘルシンキ五輪から日本選手団の公式服装を担当していた。最初の五輪は紺色のブレザーにグレーのズボンという配色だった。同7月、望月は「スポーツの宮様」と呼ばれ、当時御殿場で療養中だった秩父宮様に面会して、完成した公式服を披露した。この時の秩父宮様の言葉が、「赤いブレザー」の原点になった。
「これはブレザーではない。おそろいの服にすぎないユニホームだよ。オリンピックは4年に1度、世界の若人が一堂に会する最大の親善大会だ。一番目立つのは服装だ。日本でも学校にスクールカラーがあるように、その国々にもカラーがある。よく日本の歴史を調べて日本の色をブレザーに表してみてはどうだろう」(自伝から一部抜粋)。
ここから望月の「日本の色」探しの旅が始まった。今でこそ赤と白は日本の象徴的な「日の丸カラー」とイメージできるが、当時「日本の色」と言われて思いつく人はほとんどいなかった。望月は苦心の末、ついにその答えにたどり着く。
安城 大学の教授に話を聞いたり、図書館で文献を調べたようですが答えは見つかりませんでした。そんなある日、歌舞伎役者が「わがヒノモトの国」と言っていたのを思い出し、日本のシンボルは太陽だと思いつきます。太陽を表す国旗は世界でもまれで、日の丸も赤と白。さらに日本にはお祝いに紅白を用いる伝統があることなどから、日本の色は赤と白だと見いだします。日の丸だから赤と白という単純なものではなく、日本→ヒノモトの国→日の出が早い→太陽という過程があって、その延長線上に赤と白が出てきたということが重要だと思います。
その時から望月は五輪の「日本選手団に赤いブレザーを」と思いを募らせたが、実現までは長い時間が必要だった。

- 富士川町スポーツミュージアムに展示されている64年東京五輪の日本代表公式服
そもそも望月はどうして五輪の日本選手団の公式服装デザインという重責を任されるようになったのか。生まれは山梨県鰍沢(かじかざわ)町(現富士川町)。東京で洋服店に就職し、20歳で神田に「望月洋服店」を開業した。この神田という場所に大きな意味があった。
安城 同じ神田にあった日大の制服の指定商になったのです。戦争で休業した後、終戦の45年に日大向けの学用品店「日照堂」を開業します。制服の生地の配給再開後は洋服も扱うようになりました。当時の日大は競泳の古橋広之進を始め五輪代表選手を多く輩出していました。日照堂は古橋らと大変懇意にしていて餞別(せんべつ)を渡したりしていたようです。そんな関係から五輪の公式服を手掛ける話が出たようです。
ヘルシンキ五輪の日本選手団公式服のデザインを担当することになったが、終戦わずか7年の日本はまだ物資が不足して貧しかった。五輪では大量の生地が必要になる。懇意にしていた会社から断られた。そんな苦境を救ってくれたのが大同毛織(現ダイドーリミテッド)。橋渡しをしたのが古橋だった。
安城 51年に古橋が就職したのが大同毛織でした。その状況を考えると古橋を介して大同毛織に頼んだと思われます。当時は品質表示が義務づけられておらず、ウール60%でも純毛として売られていました。そんな時代に大同毛織はミリオンテックスという100%ウールの服地を売り出した。金もうけだけで商売をしていなかったので、採算を度外視しても協力しようと考えたのだと思われます。
製作は望月も所属していた大学の制服商の集まり「東京テーラース倶楽部」で請け負った。このデザイン、生地、製作のトリオは東京五輪まで続くことになる。
「男にふさわしくない」イメージ覆す
ヘルシンキ五輪後、望月は56年メルボルン五輪の日本選手団の公式服に赤いブレザーを採用するよう日本オリンピック委員会(JOC)に提案したが、あっさり却下された。
安城 決定権を持つJOCの服装小委員会が認めませんでした。「男が赤を着るのはおかしい」などが理由だったようです。結局、メルボルン五輪も紺とグレーの上下に決まりました。
望月は続く60年ローマ五輪で「赤いブレザー(下が白)」と「白いブレザー(下も白)」の2種類を試作。JOCに「どちらかで」と提案した。採用されたのは白いブレザーだった。
安城 望月さんはローマまで開会式を見に行ったのですが、観客にも白いシャツを着ている人が多く、白は色としてのインパクトに欠けると思ったそうです。そこで自国開催の東京こそ赤いブレザーでの思いをさらに強くしたようです。
望月もローマでの記憶を次のように語っている。「各国とも70%がナショナルカラーを服装に表現している。日本も国旗の日の丸でいくべきだとはっきり決めたわけです。朱は情熱に燃える若人の心と愛を表し、配する白は清潔感を象徴したもの」(日繊ジャーナル64年10月号)。
帰国後、大同毛織と赤の発色について徹底研究する。同社は62年に「カラーセンター」を設置し、実に3000回の試織りをした。栗原勝一社長(当時)のコメントが残っている。「オリンピックはスポーツの競技だけではなく、本質的にはその国の文化もを含めた競技である。ブレザーに具現化する服飾はその端的なものである」(同)。
そして、ついに東京五輪の公式服装に採用された。
安城 研究を重ねた結果、黄みの強い、太陽のもとで映える鮮やかな赤を再現することに成功しました。服装小委員会の青木半治委員長が「これであれば世界のひのき舞台に出しても恥ずかしくない」と賛成に回ったことも大きかった。

- 08~16年の五輪日本代表公式ウエア

- 96~04年の五輪日本代表公式ウエア
赤いブレザーが東京五輪の公式服装に決定した後、望月はこう語っている。「より速く、より高く、より強くというのがオリンピックの精神であるが、私はこれにより美しく-の五字を加えたい。オリンピックはスポーツの祭典であると同時に服飾のオリンピックでもある」(日繊ジャーナル64年10月号)。
望月が見いだした「日本の色」は、東京五輪後も受け継がれた。
安城 細かい部分の変更はありましたが、赤と白の上下の配色は88年ソウル五輪まで受け継がれました。92年バルセロナ五輪は森英恵さんのデザインで刷新されましたが、赤と白の2色が使われました。96年アトランタ五輪は芦田淳さんのデザインで下がグレーになりましたが、深い赤のブレザーは太陽を表現しておりコンセプトは受け継がれていました。夏季五輪ではレインボーカラーのマントを着用した00年シドニー五輪から望月さんのデザインは完全に姿を消しました。
ところが12年ロンドン五輪から再び赤と白の望月デザインが復活した。前年に東日本大震災が起きて、原点回帰した。リオデジャネイロ五輪では古くさいという批判も出た。20年東京五輪のデザインはまだ決まっていない。
安城 64年にどういうコンセプトで赤と白の公式服が誕生したのか。その経緯をしっかりと考えてほしい。どんなものも新しいものを作るときは、歴史を踏まえて考えないと、いいものはできない。その意味でも20年東京五輪の公式服は、しっかりと歴史を踏まえた上で、デザインを考えてほしいと思っています。(敬称略)
出身地山梨にミュージアム
望月さんの出身地の山梨県富士川町鰍沢にある「富士川町スポーツミュージアム」には、東京五輪の日本選手団のブレザーをはじめ望月さんが長年にわたって収集した五輪関連グッズなど約350点の貴重な品々が展示されている。いずれも望月さんが実家近くの蔵に保管していたもので、遺族の寄付などにより05年に開館した。地元出身で富士川町教育委員会の川口信二さんは「私が小学生の頃は学校の玄関前に望月さんのつくった赤いブレザーが飾ってありました。地元では有名でどこの学校にもあったようです」と話した。入場無料。住所は山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢4852の1、交流センター「塩の華」に併設。連絡先は富士川町教育委員会(0556・22・5361)。
◆望月靖之(もちづき・やすゆき)1910年(明43)1月7日、山梨県鰍沢町(現富士川町)生まれ。11人兄妹の10番目。小学校卒業後に親族のいた台湾に渡る。18歳で帰国し、20歳で東京・神田に「望月洋服店」を開業。戦後に「日照堂」と改名し、学用品や大学の制服などを手掛けた。夏季五輪は52年ヘルシンキ大会から76年モントリオール大会まで日本選手団の公式服装を担当。03年1月に死去した。
◆安城寿子(あんじょう・ひさこ)1977年(昭52)10月23日、東京生まれ。服飾史家。学習院大文学部哲学科卒。お茶の水女子大大学院後期課程単位取得退学。博士(学術)。お茶の水女子大などで非常勤講師を務める。JOA(日本オリンピックアカデミー)会員。専門は日本の洋装化の歴史研究。共著に「ファッションは語りはじめた」(フィルムアート社)がある。年内に光文社新書から五輪ユニホームの歴史に関する本を刊行予定。
アイビー石津謙介さん説は「裏付けなく…」
最近まで東京五輪の赤いブレザーはアイビールックで有名なデザイナー石津謙介さん(故人)がデザインしたという話が定説化していた。64年当時、公式服装の展示会では「デザイン 望月靖之」と表示され、新聞や雑誌でもそう報じられていたが、なぜか00年前後から石津デザイン説が広く流布するようになった。
「石津説は以前からファッション誌などに掲載されてきたが、NHKが放送し、JOCのホームページにも掲載されたことで、その説にお墨付きを与えてしまった。SNSなどで2次、3次の拡散が行われたことも大きい」と安城さんは分析する。石津さんは東京五輪のスタッフ用ユニホームを手掛けていたことから誤解された可能性もある。
一方で64年6月7日付読売新聞で、石津さんは「貧乏人の注文服」の見出しで、赤色の選択を評価しながらも、純毛であつらえた公式服装を批判している。「石津さんはデザインではなく監修をしたという説もありますが、裏付ける資料や証言はなく、極めて信ぴょう性は低いと言わざるを得ない」と安城さんは話した。
(2017年5月10日付本紙掲載)
【注】年齢、記録などは本紙掲載時。