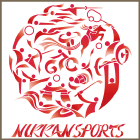政治家のように、どっちつかずな大人びた言葉は、異論はなくとも、心に刺さらない。ストレートに思いの丈が詰まった言葉は胸にグッと響く。ただ、それが過ぎると、エゴにも映る。他者への想像力を欠くと、波紋を呼ぶこともある。物事の伝え方は本当に難しい。学校でも、ビジネスでも、恋愛でも、生きていく上で普遍的なテーマである。
今、選手に東京オリンピック(五輪)・パラリンピックの思いを聞く。その答えの多くには、前置きが付く。「開催できるか分からないけど」「コロナが終息すれば」。そして思慮を巡らせ、言葉を選び、遠慮がちな表情になる。
開催が決定し、あれほど沸き立ったのは、もう7年半前。今や世論の目は厳しい。コロナの終息は見通せず、最近では女性蔑視発言も機運の低下に追い打ちをかけた。そんな中、堂々と「五輪を開催して欲しい」と声を上げることは難しい。8割以上が開催に否定的という世論調査もある。現代人に欠かせなくなったSNSは共感だけでなく、敵愾(てきがい)心まで浮き彫りにする。
大会への嫌悪感はいいが、怒りの刃がアスリートに向いてはいけない。その大前提は成り立っていると信じた上で、記者として思う。選手は五輪・パラリンピックの開催を願うのであれば、その発信、意思表示に遠慮などいらない。胸を張って、言っていい。感情を抑制することもない。だってアスリートなのだから。
厳しき世界を生きる。結果を残さなければ、生活が保証されない人もいる。重圧と闘いながら、血のにじむような努力を重ねてきた。競技が仕事。そしてスポーツで社会に活力を与えるのが使命でもある。もう現役中に、母国で五輪・パラリンピックをできるチャンスはない。大げさでなく、人生を懸ける舞台の開催を願うのは当然で、それが否定されていいわけはない。
2月に女子ソフトボールの上野由岐子(38=ビックカメラ高崎)から聞いた言葉が耳に鮮明に残る。「世界中がコロナと闘っているからこそ、勇気付ける意味も含め、五輪の開催は大きな意味があると思う」。前置きなき、野心にあふれた決意だった。去年の春までは、幾多の人から何度も何度も聞いていたはず。それが、いつしか新鮮になっていたからだろう。事態を楽観視しているわけでも、現実を軽く考えているわけでもない。アスリートの矜持(きょうじ)に満ちる言葉は、自粛の時代でも色あせずに響く。【五輪担当 上田悠太】