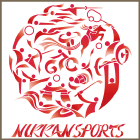2度目のオリンピック(五輪)イヤーが始まった。新型コロナウイルス感染症で仕切り直しになった東京五輪は7月に開幕を予定。だが依然としてコロナ禍の先行きは不透明なままだ。13年9月の開催決定から7年4カ月。「記者が今、思うこと」と題し、現場記者の考えをコラムでつづる。
◇ ◇ ◇
大みそかの12月31日で、自宅のインターネットがつながらなくなった。大阪から東京に転勤して、単身赴任で4年。ネット回線はキャンペーンだの、通信費24カ月割引だの、2年縛りの契約が多くて、ややこしい。20年12月で契約終了としていたが、コロナ禍で東京五輪が延期されて、単身赴任も延長。年明けからプロバイダー変更の手続きが、煩わしい。ただオンライン取材が当たり前となった今、自宅にネット回線なしでは仕事もままならない。
昨年末、日本オリンピック委員会山下泰裕会長(63)に1年の感想を聞いた。同会長は「1年前は、まさかコロナ禍がこんなに世界を混乱させて、人々に多大な影響を及ぼすとは考えられなかった。五輪が延期するなんてね」とぽつりと言った。1年前は五輪イヤー幕開けとしてスポーツ界に高揚感があった。だが2度目の今年は感じられない。
1年延期で、状況が変わった選手も多い。競泳萩野公介は1年前、五輪出場も危うい立場だった。泳いでも、タイムが上がらない。それが昨秋のブダペスト遠征から一気に復調した。1カ月で5大会という連戦が「レースが怖い」という感覚を忘れさせた。白血病から復帰した池江璃花子は400メートルリレーで東京五輪に出る可能性がかすかにある。ドーピング検査陽性があった古賀淳也、藤森太将は延期の間に資格停止が明けて、五輪に挑戦できる。一方で女性問題で2カ月半の活動停止となった瀬戸大也のようなケースもある。水泳の1種目である競泳だけでこれほどの変化がある。
選手だけではない。延期に伴って、組織委、自治体、企業でも多くの人の人生設計が変わっただろう。記者の周りだけでも、担当替え、転職、定年と数知れない。コロナ禍=東京五輪延期は、現時点でも国民の記憶として刻まれただろう。
自国五輪は、良くも悪くもビッグイベントだと痛感する。自宅のプロバイダー変更は大したことではないが、多くの人に今以上の努力を求める「22年再延期」は到底、受け入れられないだろう。開催か中止か。どちらにしても、東京五輪は今年で決着をつけるしかない。できれば、ポジティブな記憶として人々の心に刻まれてほしい。【五輪担当キャップ 益田一弘】