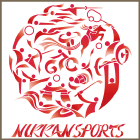今から100年前の1920年8月14日、ベルギーでアントワープ・オリンピック(五輪)の開会式が開催された。初めて五輪旗の掲揚と選手宣誓が実施され、テニスで熊谷一弥が銀メダルを獲得して日本人初のメダリストとなった大会でもある。一方で世界に甚大な被害を及ぼした第1次世界大戦(14~18年)とスペイン風邪(18~20年)の直後の大会で、コロナ禍で来年に延期された東京五輪とも状況が重なる。どんな大会だったのか。当時の資料をもとに振り返る。【首藤正徳】
■復興が最優先
アントワープ五輪のテニスで銀メダルを獲得した熊谷は、自伝『テニスを生涯の友として』(講談社)で大会の詳細を記している。決勝で敗れた夜の心境を「この夜ほど私は悲憤痛恨の涙にくれたことはない」と振り返り、大会自体もこう酷評している。
「設備も不完全、秩序は不整頓で(中略)コートの手入れの悪さ、これがオリンピック大会の晴れの檜舞台とはお世辞にも申しがたい(中略)試合進行の方法がまた無茶苦茶(中略)出場選手の迷惑などおかまいなしだった」
「選手ファースト」どころではなかったようだ。無理もない。4年に及んだ第1次世界大戦が18年11月に終結したばかり。翌19年3月の国際オリンピック委員会(IOC)総会でアントワープが8年ぶりの五輪開催地(16年ベルリン大会は中止)に決まった。しかし、準備期間はわずか1年あまり。しかも、戦災でベルギーは甚大な被害を受けていた。
■選手にしわ寄せ
加えて18~20年にかけてスペイン風邪が世界を席巻した。当時、死者数は全世界で2500万人と言われた。これは1800万人といわれる第1次世界大戦をはるかに上回る。欧州では230万人が犠牲になった。当時、人々は今日を生きるのに精いっぱいだった。
そんな中でIOCはあえて五輪開催を決断した。特に戦火のひどかったベルギーで五輪を開催することで、世界中で平和の喜びを分かち合おうと考えたのだ。アントワープの貴族たちも招致に動いた。しかし、国民の救済を優先するベルギー政府からの援助は乏しく、スタジアムは完成したものの、大会自体は深刻な経費不足、準備不足だった。
時代背景は異なるが、この状況は来年に延期された東京五輪とも重なる。
しわ寄せは選手たちにきた。ディビッド・ゴールドブラット著『オリンピック全史』(原書房)に詳しい。「オランダチームは港に係留された船に押し込まれた。射撃の選手は大半が軍のバラックに泊まらされた。安ホテルは選手たちで大混雑だった」「(米国競泳陣はプールを)『土手に囲まれた水路に黒くて冷たい水をためたようなもの』とこきおろしている」。
一方、スペイン風邪で未曽有の犠牲者を出したにもかかわらず、感染予防の対策は重要視されていなかった。ここは来年の東京五輪とは大きく異なる。流行が収束へ向かっていたことや、もともと病死の死亡率が今よりもずっと高かったという背景もあった。当時は祖国のために戦って亡くなった第1次世界大戦の戦死者の追悼や、戦災からの復興が大衆の最大の関心事だった。
■参加国最多も
それでも大会には史上最多29カ国から2591人の選手が参加。開会式ではクーベルタンIOC会長が考案した五輪旗が掲揚され、初めて選手宣誓が行われた。しかし、地元紙ド・スタンダールは「『特別観覧席は満員だったが、一般観客席はガラガラだった』と報じた」(『オリンピック全史』より)。1週間後に入場無料としたが、地元ベルギーが優勝したサッカーなどをのぞいて、観客は増えなかった。
公式報告書は「卓越した統率力をもって完璧かつ厳かにおこなわれた」と総括したが、地元のオンス・フォルク紙は「公共の利益という点では失敗に終わった」と報じた。主催者側と地元の反応は見事にかい離している。
実は経費削減や紙不足などの影響で、アントワープ市民に五輪について告知宣伝がほとんどされていなかった。なぜ、この時期に開催するのか、平和の祭典の意義を理解している人も少なかった。当初、入場料が一般市民には手が届かない値段に設定されたことも、大衆の無関心に拍車をかけた。地元の協力、一体感が得られなかったことが、大会運営にも大きく影響したのである。
コロナ禍という世界的な災厄の収束が見えない中、日本政府と東京都は東京五輪の延期開催を決断した。一方で7月の共同通信の世論調査では予定通りの開催を望む声は3割に満たない。五輪を真の成功に導くのに最も必要なのは、地元の人々の理解と協力、一体感である。それはいつの時代も変わらない。開幕まであと1年。100年前の苦い経験を、反面教師にしてほしい。
■日本は2度目の参加
日本にとってアントワープ大会は、初参加した1912年ストックホルム大会以来2度目の五輪だった。前回は陸上短距離の三島弥彦とマラソンの金栗四三の2人だけだったが、陸上、競泳、テニスに15人が出場した。18年秋から20年にかけて日本でもスペイン風邪が大流行。感染者約2380万人、死者38万8000人と甚大な被害を及ぼしたが、今ほど情報網が発達していなかったためか、選手団が特に感染防止に対策を講じた記録はない。
15人のうち日本在住の13人は5月14日に横浜港を出発。太平洋と米大陸、大西洋を横断して米国と英国を経由する行程だった。その理由について日本選手団の主将を務めた野口源三郎は著書『第七回オリンピック陸上競技の印象』で「スポーツ先進国の両国を訪ねて、技術と見識を高め、勝負度胸をみがくため」と記している。
5月30日に米サンフランシスコに到着。約40日間、米国大陸を汽車で横断しながら、シカゴやニューヨークなどの大学で著名コーチの指導を受けて練習を積んだ。7月19日のロンドン着後は約20日間、現地の大学などで世界トップ選手らとも練習した。アントワープ到着は8月7日の夜だった。
割り当てられた宿舎は小学校の教室で寝具は軍隊用のものだった。しかし、現地の日本公使館(当時)の協力で食事は和食が提供されるなど選手らは与えられた環境に満足していた。「味噌汁と沢庵を味ふことも出来て全く旅愁を拭ひ去ることが出来たのである」と野口も記している。
大会では商社の米国支店に勤務していた熊谷がシングルスと、柏尾と組んだダブルスで2つの銀メダルを獲得したが、陸上と競泳陣は惨敗に終わった。大会後、米国在住の熊谷らをのぞく日本選手団はマルセイユから航路で帰国の途についた。神戸港到着は出発から半年たった11月6日未明だった。
◆アントワープ五輪 16年ベルリン大会が第1次世界大戦で中止されたため、8年ぶりの五輪だった。20年4月20日~9月12日まで開催された。期間が長いのは冬季競技のフィギュアスケートとアイスホッケーが実施されたため。開会式は8月14日。23競技154種目が行われた。射撃の団体で72歳のスバーン(スウェーデン)が手にした銀メダルは、今でもメダリストの最年長記録。後に陸上長距離で五輪通算9個の金メダルを獲得したヌルミ(フィンランド)が初出場し、3種目で優勝した。
◆スペイン風邪 第1次世界大戦中の18年3月に米国の陸軍基地で発生し、欧州派兵で世界に拡大したとされる。参戦国が死者などを機密とする中、中立国スペインで大きく報じられたことで『スペイン風邪』と呼ばれるようになった。18年春からの第1波は軽症者が多かったが、夏以降の第2波で死者が急増。流行は19年の第3波まで続き、日本では21年まで続いた。死者は米国60万人、欧州230万人、インド1250万人、日本38万8000人など全世界で甚大な被害をもたらした。当時、死者2500万人とされたが、現在では5000万超だったと推測されている。
◆第1次世界大戦 1914年7月から18年11月にかけて欧州を主戦場に25カ国が参加した人類最初の世界戦争。連合国(ロシア、フランス、英国など)と同盟国(ドイツ、オーストリア・ハンガリー帝国など)による戦いで、17年に連合国についた米国が参戦して拡大。連合国の勝利に終わった。戦争の過程でロシア革命が勃発してソビエトの労働者政権が誕生した。日本は日英同盟を理由に連合国側について中国のドイツ領などを占領した。全世界で兵士900万人、一般市民900万人が犠牲になったとされる。
<参考文献>
『テニスを生涯の友として』(熊谷一弥著、講談社)
『第七回オリンピック陸上競技の印象』(野口源三郎著、中文館書店)
『オリンピック全史』(ディビッド・ゴールドブラット著、志村昌子、二木夢子訳、原書房)
『近代オリンピック100年の歩み』(ベースボール・マガジン社)
『流行性感冒』(内務省衛生局編、平凡社)
『人類対インフルエンザ』(トム・クイン著、山田美明、荒川邦子訳、朝日新聞出版)
『国際化時代「大正日本」』(桜井良樹著、吉川弘文館)