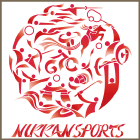選手村から出る大量の食品廃棄物が昨今、五輪では大きな課題だ。日本において、まだ安全に食べられる「食品ロス」の総量は約646万トンに上り、コメの年間生産量約782万トンと比べると深刻さは明らか。20年東京五輪組織委員会は解決策を検討中だが、民間では現在進行形で多角的な取り組みが実施されている。今回、「フードバンク」や「食品ロス救済アプリ」を運営するNPO法人や企業を取材。東京大会の取り組みの遅れを指摘する声も上がった。【三須一紀】

- セカンドハーベスト・ジャパンのマクジルトン・チャールズCEO(撮影・三須一紀)
浅草橋駅にほど近いJR総武線のガード下、平日の午後2時に20~30人が列を成した。シングルマザー、外国籍の難民らを含めた生活困窮者が食材を求めて並んでいた。
NPO法人「セカンドハーベスト・ジャパン」のパントリー(食品貯蔵所)活動で、生活困窮者に食材を手渡しで提供する。並んでいるのは日持ちする加工食品だけではない。この日は、ホウレンソウ、レタス、トマト、タマネギ、ジャガイモ、ニンジン、インゲン豆、パクチー、バナナなどの種類豊富な野菜や果物、しゃぶしゃぶ・しょうが焼き用の豚肉も並んだ。
同団体は他に「フードバンク」システムを日本で初めて導入し、02年から実施。食材を児童養護施設や福祉施設、DV被害者シェルター、路上生活者のもとに届けている。運営と食材、食品、全てが寄付で賄われる。食品加工工場、卸業者、スーパーや食品メーカー、農家などと契約を結び余剰品を仕入れ、需要のあるところへ分配する仕組み。食べられない人がいるのに食品ロスが起きる、社会の「矛盾」を埋めることが、彼らの職場だ。
組織委が今年3月に策定した「飲食戦略基本計画」第1版では食品ロス削減案として(1)ポーション(1人前料理盛りつけ量)コントロール、(2)情報通信技術(ICT)管理、(3)飼料、肥料化を挙げた。そもそもの食品提供量を管理し、食品ロスを防ぐ狙いだが、余剰がゼロになることは考えにくい。
大会期間中に200万食を提供する選手村では24時間体制で、スムーズに食事提供することが求められ、カフェテリア方式が主流。世界中の国、民族の食事に対応するため多種多様なメニューも準備する。衛生管理上、提供できるのは調理後2時間以内という厳しい取り決めもある。食べ残し以前に、選手が手すら付けずに配膳不能な食事が出ることになる。
元米海軍の創立者マクジルトン・チャールズCEO(54)は14年から毎年、組織委や東京都の担当者と会い「フードバンク」を東京大会でも導入すべきと訴えてきた。しかし、反応はいまいち。寄付文化の成熟とはほど遠い日本社会の縮図を見たようだったという。
チャールズ氏によると、生活困窮者向けのパントリーの数は、米ニューヨークが約1200カ所、中国・香港で約160カ所だが、東京は約10カ所(同団体関係施設)と圧倒的に少ない。米国で67年に世界初の「フードバンク」ができたことを皮切りに、欧州やアフリカにも広がった。
「日本はさまざまな分野で世界的な評価が高い国。当然、世界のメディアは日本の食品ロス対策、寄付文化も取材する。選手も同じで、この分野への感度は高い。このままでいいのだろうか」と首をかしげた。
17年5月、組織委内の資源管理ワーキンググループで1人の委員がある調査を公表。選手村だけでなく12年ロンドン大会全体の食品廃棄量は2443トンだったという。ただ、この数字は可食部と非可食部を混在している可能性があり、組織委は1500トンだったと推計している(大会全体の食事提供は1500万食)。いずれにせよ、膨大な廃棄量だ。
記者は実際、16年リオデジャネイロ大会で「フードバンク」の試みを取材した。ただし、リオ大会の廃棄量は具体的に示されておらず、ロンドンから改善されたかは分かっていない。
チャールズ氏は組織委に提案した際、「予算がない」と断られたが「廃棄より、フードバンクの方がお金はかからない」と話す。仮に、食品10トンの廃棄に100万円かかるとすれば、「フードバンク」は10万円でできると主張した。
飼料・肥料化案について「人間が困っているのになぜ人間に回さないのか」と疑問符。衛生面に最大限配慮することを前提に「五輪選手の食事と同じものが児童福祉施設に届いたら、子どもたちは非常に喜ぶだろうし、五輪に前向きになれる」と語った。
同団体に食品提供している企業・団体は昨年で1445団体にまで拡大。それでも日本の寄付文化は草創期といい「日本は社会のセーフティーネットを行政に任せきり。世界は、できることは自分たちでやろうとする」という。
確かに運営側には、外に回した余剰食材・食品が原因で食中毒が発生する危険性を排除したい思惑もある。ただ、チャールズ氏は安全面の考慮は最前提としたうえで「持続可能性、イノベーティブな大会にするチャンスをみすみす捨てないでほしい。税金を使って、食べられるものを廃棄するのは間違っている…」と、切に語った。
◆セカンドハーベスト・ジャパン 00年、炊き出しのために食材を集める活動を始め、02年に日本初のフードバンク活動を開始。今年4月には東京都より認定NPO法人の資格を取得した。食品ロス問題に関心が集まり、協力企業・団体数は年々伸びている。02年時は3件だったが09年に144件、13年は469件、そして17年は1445件と急増中だ。スーパーの西友などは生鮮食品などで積極的に協力する企業の1つ。一方で、企業名を明かさず協力するケースも多い。「無料で配るなら、一般消費者にももっと安くできる」などと苦情を受けるリスクがあるからだという。関係者は「世界には無料スーパーがある国もある。日本はそれだけ寄付文化が遅れている証拠」と語った。食品の直接配給の他に、児童養護施設などの約300団体にも寄付する。内訳は児童養護施設が最も多く24・6%、生活困窮者支援施設20%、障がい者施設13・2%、母子支援施設も6・5%。1食あたりの提供コストは約25円だという。

- セカンドハーベスト・ジャパンで生活困窮者に配られる食材はさまざまな企業から届けられる(撮影・三須一紀)
■アプリで救済 飲食店から会員へ
“食品ロス救済アプリ”を開発する会社「コークッキング」が東京・南麻布にある。サービス名は「TABETE.ME」。4月に運営を開始したばかりで、現在はウェブ版だが、9月にはアプリ版を開始する予定という。
「TABETE」に登録した飲食店、総菜店などの店舗に余剰食品が出た場合、その商品が同サイトに掲載される。一方、会員となっている消費者側は、その情報を閲覧し、好きな商品を購入予約。実際に店舗に足を運び、商品を受け取るという仕組み。登録料は無料だが、売れた分の35%がマージンとなるビジネスモデルで、そのうち5%が子ども食堂へ寄付される。

- 「TABETE.ME」のサイト
現在、登録店舗は渋谷区、港区が中心で約120店舗。利用登録者数は約1万8000人にものぼった。路面店などは雨が降るだけで客足は激減し、食品ロスが一気に増える。同サービスではロスしそうな商品を買うことを「レスキュー」と呼ぶ。
食品ロスを防ぐという観点を重要視する川越一磨CEO(26)は「ただのEコマースサイトになってはいけないので、なぜその食品が余ったのか、店舗側にストーリーを添えてもらっている」と語った。将来的にはアジアや食品ロスへの感度が高いオセアニアへの進出も視野に入れる。
現時点で話はないが「東京五輪でこのようなシステムが使えたら面白いのでは」と川越氏。選手村の食事を一般人が食べるだけで「インセンティブ(動機づけ)が発生する」と語った。
組織委が飼料・肥料化を検討している点については「食べられるうちに食べるのが一番、環境負荷は小さい。食べてもらえる人がいるのに、なぜ飼料にするのか」と話した。競技会場などで出る食品ロスにも注目し、「今日は何時に○○スタジアム脇で引き渡します」などとすれば、同システムが活用できると、アイデアが次々と飛び出た。
■リオでは有名シェフが無料でフルコース提供

- 給仕作業をした記者を労う世界的シェフたち。左からダヴィ・ヘルツ氏、カルロス・ガルシア、マッシモ・ボットゥーラ氏(撮影・エリーザ大塚)
16年リオデジャネイロ五輪で記者は、大量に食事が提供される選手村やMPC(メインプレスセンター)の余った食材を使い、ホームレスらに無料で食事を提供するプロジェクトを取材した。同年「世界のベスト・レストラン50」で1位に輝いた世界最高のイタリア人シェフ、マッシモ・ボットゥーラ氏(当時53)らが企画した。
来店したのはファベーラ(貧民街)にも住めないホームレス40人と、強い差別を受け、職に就けないゲイ16人。5歳ぐらいの男の子を連れた母親もいた。来店者への撮影はNG。担当者は「彼らの尊厳を奪ってはいけない。我々は彼らを尊敬している」と徹底した。
この日、責任料理長はベネズエラのトップシェフ、カルロス・ガルシア氏。同国のフルコースを振る舞った。
約2カ月前まで、何もなかった場所に仮設施設を建てた。だが内装は高級レストラン風。野外での炊きだしでなく、普段味わえない、温かく落ち着いた場所での食事を提供した。日本の「炊きだし」ではあまり見られない風景だった。
食材の調達先は世界の技術や富が結集する「五輪」。選手村では少しでも不格好な野菜は使わない。熟して赤くなりすぎたトマトは「サラダには向かない」と判断され、通常だと廃棄処分だったが、それをリオ五輪組織委などと交渉し、もらい受けた。「食材はあり過ぎて2日前に来たものを使った。五輪には物も無駄遣いも多すぎるのだろう」とガルシア氏は言った。
「貧困救済レストラン」は約40日間営業。ランチを通常営業し、そこで集めた資金を運営費に回して夜は毎日、貧しさと飢えに苦しむ人たちに、温かい食事を提供していた。