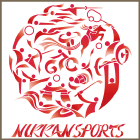仕事をする上でずっと頭にある言葉がある。
「生きている価値は、どれだけ人の役に立てているかが大きいと思うの」
数年前のテレビ番組でマツコ・デラックスが定職に就かない若者に持論を語った時の言葉で、記事を書く時に「この記事は誰かの役に立つだろうか」とぼんやり考えることが多い。
「人の役に立ちたいんです」。同じ言葉を聞いたのは昨年12月。同6月で現役を引退した元トランポリン選手の外村哲也さんからだった。「五輪は誰もが経験できることではない。貴重だからこそ、経験したことで気付けた学び、それを伝えていくべきものとしてとらえています」。役に立つための原資は、4位入賞した08年北京五輪の体験であり、その後も五輪出場を目指して送った日々。特にビジネスなどに精神面を活用するメソッドを重視し、「メンタルクリエーター」の肩書を今は持つ。
何で自分は役に立てるのか。自問は必然、自分の価値を考えさせる。外村さんは12年ロンドン五輪代表に落選し、所属先から契約を打ち切られ、自らスポンサー探しで営業する日々で、対価として返せる「価値」を考え抜いた。社員向けのメルマガなどで「経験をシェア」することは、現在の肩書につながる芽生え的な動きだったが、不十分だったと振り返る。「恵んでもらっていた」。卑屈ではなく、実直に振り返る。
競技以外に提供できる価値とは。コロナ禍で、試合を奪われた選手の多くは、考えたのではないか。アマとプロの境界線が曖昧で、所属先の業務を行わずに競技に専念できていた選手も多い。コロナ以降、アスリートの企業による支援は厳しさを増す。国からの助成金も含め、ある種の「保護膜」に包まれていた環境が、突然寒風にさらされる。その時、何が自分の価値で、何で役に立てるのか。
例えば、大坂なおみなら黒人差別問題に発言することが「価値」である。選手が社会問題にコミットしていくことで、それが誰かの役に立つ可能性もある。東京五輪の開催可否にかかわらず、日本社会におけるスポーツの価値は、アスリートが考えた自らの「価値」でしか、醸成されない。そして、その「価値」を伝える記事を書けたら、それが記者にとっての「生きる価値」だと思っている。【五輪担当 阿部健吾】