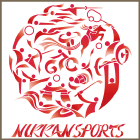「記者さんは、会場には入れるんですよね?」
「記者は予約制なんですが、今のところ、たぶん入れるかなと思っています」
「そうですか。応援してやってください。息子を応援してやってください。きっと届くと思うんです」
最近、切ない気持ちになる言葉を聞く機会が増えた。
五輪開幕を控えて、選手にゆかりがある人を取材する。その際に話題になるのは、無観客開催、そして東京オリンピック(五輪)を取り巻く状況だ。
「もうニュースを見るのも、聞くのもつらくて」
「こんなご時世なので、代表になっても喜ぶというわけにはいかなくて」
なぜ夢である五輪をつかんだ選手の関係者が後ろめたさを感じなければいけないのか、割り切れない。コロナ禍で困っている人たちがいることは、頭ではわかっている。しかし、いざ目の前でゆかりの人たちが困惑する顔を見ると胸が痛い。
小さなころ、子どもがあるスポーツに夢中になった。ただ喜ぶ姿が見たくて、試合会場に足を運び、練習場に送り迎えして、早起きして弁当を持たせる。競技成績が出れば、わが事のようにうれしい。泣いて悔しがる子どもを見て、何と声をかけていいのか、言葉につまる。そんな日々が積み重なって気がついたら五輪選手になっていた。親も含めて周囲の人は「まさか五輪に出るなんて」という感想がほとんどだ。しかし今大会は応援にいくどころか、応援すること自体に申し訳なさを感じている。
五輪は通常4年に1度だが、選手個人にとっては違う。2度、3度と出る選手はほんのひと握りだ。ほとんどの選手は、20年近くかけて一心不乱に練習に励んだ末に、やっとたどり着く。海外勢も含めて約1万人の参加選手が膨大な時間をかけて重ねてきた努力。それを0か100かで切り捨てるような意見を目にするのは、あまりにも悲しい。
50年後、100年後に今大会の写真や映像を見れば、後世の人々はきっと驚くだろう。無観客の異様な会場に象徴されるように、開催こそが最大の贈り物だと、選手も、ゆかりの人たちも、もう十分にわかっている。だから、せめて人生をかけて全力を尽くした直後は、たくさん喜んで、たくさん泣いて、たくさん笑ってほしい。【五輪キャップ 益田一弘】