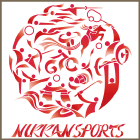五輪のたびに注目される、もう1つの“対決”がある。日本が誇る2大カメラメーカーのシェア争いだ。望遠レンズの外装が「白」のキヤノンと「黒」のニコンは、4年に1度の世界最大の祭典をターゲットに毎回、技術革新された新機種を投入してきた。そのし烈な戦いは「白黒戦争」とも呼ばれ、長年に及ぶ切磋琢磨(せっさたくま)が画像技術を飛躍的に進歩させた。戦いの舞台が自国となる2020年東京五輪では、さらなる進化が期待されている。【取材・首藤正徳、山崎安昭、江口和貴】

- カメラの変遷を説明するニコンイメージングジャパンの森執行役員(撮影・山崎安昭)
1964年東京五輪のカメラマン席は、ニコンのカメラで埋め尽くされた。シェアはほぼ100%。手にしていたのは59年に発売された「ニコンF」。同社初のレンズ交換式一眼レフで、絞りと露出計の連動や、毎秒3・6コマのモータードライブ(連写装置)の実用化など世界初の機能が搭載されていた。
実は1年前のプレ五輪では大半が米国製の大判カメラを使用していた。ニコンイメージングジャパンの森真次執行役員が大転換の理由を明かす。「ニコンのレンズがニューヨーク・タイムズで紹介されるなど米国で高く評価されて、ニコンは日本よりも海外で普及しました。プレ五輪で欧米のカメラマンが使っていた機材を見て、その性能に驚いて、日本の報道各社が一気に切り替えたと聞いています」。
そこからニコンは報道・スポーツのプロ仕様のトップブランドとして一気に世界に定着。信頼性や耐久性の高さが認められ、あのNASA(アメリカ航空宇宙局)でも採用された。キヤノンがようやく報道向けに一眼レフ「F-1」発売したのは71年。連続撮影10万回に耐える耐久性で、開発に5年の歳月をかけた。もっともニコンも80年に毎秒6コマ連写が可能な「F3」を発売するなど、高い技術力でライバルの追随を許さなかった。
キヤノンマーケティングジャパン・イメージコミュニケーション企画本部の相川弘文本部長は当時を振り返る。「64年当時、弊社には報道現場で使えるような耐久性のある機材がなかった。71年に初めてF-1が出て、それから10年かけてお客さんの声を集めて、81年に『NewF-1』を発売しました。そこから少しずつ使ってもらえるようになりました」。
この81年にキヤノンは後の「白黒戦争」の原点ともいえる製品を発売する。NewFD300ミリF2・8L。初めて第一線のプロに認められた白いレンズだった。「“レンズは黒が当たり前”という認識が変わりました。ボディーが黒いと夏場は熱を吸収するので、それを防ぐために白色に塗布したようです。ニコンさんへの対抗意識もあったと思います」(相川氏)。
高額なテレビ放送権料やスポンサー協賛金で商業化に転換した84年ロサンゼルス大会以降、五輪の注目度は世界中で急騰した。「白黒戦争」もさらに激しさを増した。「第一線のプロがどのカメラを使っているか、全世界に中継される。当然、商品開発も五輪にベクトルが集中します」(森氏)。「プロが使うカメラ=高画質という印象がありますから、宣伝効果としては圧倒的です」(相川氏)。ロサンゼルスはキヤノン、88年ソウル五輪はニコンが協賛社に名を連ねた。
80年代末、オートフォーカス(AF)時代に突入して、ようやくキヤノンが頭角を現す。当時はカメラマン自身がピントを合わせていたので「AFはプロが使う機材ではない」との声も根強かったが、89年に発売した「EOS-1」でAF機能を飛躍的に向上させ、曲線を意識したデザインも人気を呼んだ。一方、ニコンもアトランタ五輪が開催された96年に秒間8コマ高速連写の「F5」を発売して、プロをうならせた。
90年代終盤にデジタル化の時代が到来して、2社の開発競争はさらに激化した。特に99年にニコンが発売した「D1」は、デジタル一眼レフの市場を拡大させた。周囲を驚かせたのがその販売戦略。これまで200万円前後だった定価を一気に65万円と3分の1に下げて大好評を博した。「大量に売れることを想定して思い切ってコストを下げました。デジタルが普及するきっかけにもなりました」と森氏は振り返る。

- 歴代のカメラについて説明するキヤノンマーケティングジャパン相川弘文氏
一方「キヤノンも98年に発売したD2000が、デジタルカメラでの取材のスタートとなりました」と相川氏。もっとも00年シドニー五輪は65対35でまだフィルムが上回っていた。シドニー五輪前にキヤノンが発売したフィルムカメラの「EOS-1V」も健闘した。
04年アテネ五輪でカメラ市場に大きな変化が起きた。大会前にキヤノンが発売した「EOS-1D マーク2」が、圧倒的な支持を獲得したのだ。「フィルムがなくなり、写真の色はカメラがつくる時代になりました。この機種はノイズが少なくクリアな画質でAFの完成度も高かった」と、相川氏はその理由を説明する。アテネ五輪のカメラマン席は白いレンズがずらりと並んだ。ついにキヤノンがニコンを大逆転したのだ。
このカメラの性能の高さを象徴するあるエピソードを相川氏が明かした。「五輪後の04年10月、中越地震で新聞社のカメラマンがヘリコプターに救助される少女をこのカメラで撮影したら、暗闇の中でも被写体がはっきり写っていたため、性能の高さが再認識されました」。
キヤノンの1強時代到来かと思われたが、ここからニコンが底力を見せた。北京五輪前年の07年に超高感度のフルサイズセンサーを搭載した「D3」を発売。ノイズの少ない圧倒的な高画質が評判となり、ニコンへの逆流が始まった。「このままではニコンユーザーがいなくなるといわれていた時期に起死回生で出した機種でした。翌年の北京五輪では半分近くまでシェアを戻したようでした」と森氏は振り返る。
16年リオデジャネイロ五輪ではキヤノンが「EOS-1DXマーク2」、ニコンは「D5」と、さらにカメラの精度を高めた商品を投入。ほぼ互角の戦いだったといわれた。
それにしてもなぜ五輪で日本の2大メーカーが圧倒的に支持され続けるのか。「キヤノンもニコンさんも、カメラやレンズの性能はもちろんですが、地道に築いてきた信頼関係が大きいと思います。五輪でもサービス拠点に大人数を派遣して、万全のサポート態勢を構えていますから」と相川氏は力説する。
20年東京五輪はキヤノンが協賛社になった。ただ、ニコンの森氏はこうも語る。「プロが使うカメラと、スポンサーとはまた別の話。今後のニコンに乞うご期待と言うしかない。これまでもライバルと激しい切磋琢磨があったから、より性能のいいものをつくり出してきましたから。考えてみると、両方とも黒、あるいは白だったら、今のようにはなっていないでしょう」。2年後へ向けた、両社の新たな戦いはすでに始まっている。
◆キヤノン株式会社 1937年(昭12)、精機光学工業として創業。33年に東京に設立された精機光学研究所がルーツ。34年に試作した国産初の35ミリカメラを観音様の慈悲にあやかり「KWANON(カンノン)」と命名。翌年に英語で「聖典」「規範」「標準」という意味がある「CANON」としたのが社名の由来。戦後に社名を「キヤノンカメラ」とし、69年に「キヤノン」に変更した。本社は東京都大田区下丸子3の30の2。御手洗冨士夫会長 CEO。
◆株式会社ニコン 1917年(大6)、前身の日本光学工業として創立。主に海軍向け光学機器の国産化を担った。第2次世界大戦後はカメラや顕微鏡など民生用光学機器の生産に転換。48年(昭23)に初の小型カメラ「ニコン1」を開発し、59年に初の一眼レフカメラ「ニコンF」を発売して世界的な評価を得る。71年にはカメラが月面探査船アポロ15号に採用される。88年に現在のニコンに社名を変更した。本社は東京都港区港南2の15の3。牛田一雄社長。