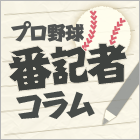中日に誕生した外国人捕手、A・マルティネスが話題を集めている。球界では、同じく中日の00年ディンゴ以来20年ぶりの出来事だ。NPBに外国人枠ができたのが1952年(昭27)であるため、それ以前に来日した場合、規則上「外国人」とは表されない。だが日本プロ野球の創生期に、海を渡ってやってきた助っ人選手の1人もまた、キャッチャーだったことは意外と知られていない。プロ野球初年度1936年(昭11)から3年間日本でプレーした、バッキー・ハリス選手だ。
かつての助っ人選手のその後の人生を追った、慶大名誉教授・池井優氏の名著「ハロー、スタンカ、元気かい」にその人生が詳述されている。A・マルティネスの所属する中日の前身、名古屋軍は、国内選手の獲得で巨人や阪神に後れを取った。そこで積極的に海外選手の獲得に乗り出した。ロサンゼルスの日系人チーム「LA・ニッポン」で、仕事のかたわらプレーしていたハリスを入団させた。
陽気で真面目なハリスは、すぐ日本に溶け込んだ。「尋常小学校国語読本」を買い込み「サイタ、サイタ、サクラガサイタ」といった文章からカタカナを瞬時に覚えた。「桃太郎」の有名な一節「大きな桃が、ドンブラコ、ドンブラコと流れてきました」を目にし、監督やチームメートに「この『ドンブラコ』とはどういう意味だ」と問い、誰も満足のいく説明ができなかったという逸話が残っている。
37年にイーグルス(現在の楽天とは無関係)に移籍したハリスは、秋のリーグで最高殊勲選手に選ばれた。49試合に出場し1本塁打ながら、24打点、打率3割1分。春のリーグは最下位に終わり、弱体だった投手陣を巧みなリードで引っ張った。チームは13連勝を飾るなど、3位に浮上した。これが評価されたのだった。
翌38年を限りに帰国を決意したハリスは、後楽園での引退試合であいさつに立った。イーグルス河野安通志代表に翻訳を頼んだ。
「職業野球は、皆様のお引き立てがなければ立ちゆきません。今後ともごひいきに願います。私はこの際、別れを告げます。皆様のご壮健と、ご幸福を祈ります。さようなら」
こんな文言の日本語の原稿を、アルバムに貼り大切に保存していた。
1976年(昭51)7月に取材した池井氏と別れる際には
「あなたもお達者で」
と、なんとも古風なあいさつで見送ったという。「70年代後半に、そんな言葉を使う日本人はいませんでした。古きよき時代の言葉が、彼によって冷凍保存されていたんです」と池井氏は述懐する。
ハリスは第2次大戦中に、米軍の通訳へと転身。レイテ島勤務となり、日本軍捕虜の通訳となった。すると「イーグルスにいたハリスさんじゃありませんか」と話し掛けられた。その捕虜は阪急軍の補欠捕手で、ハリスのプレーをよく覚えていた。おかげで捕虜の雰囲気が、一気に好転したという。
人望の厚かったハリスは帰国から38年後の1976年(昭51)10月21日、池井氏らの尽力で日本に招かれた。懐かしい後楽園で、巨人-阪急の日本シリーズ第1戦を観戦。5万人を超える大観衆に感銘を受け、日本プロ野球の隆盛を大いに喜んだ。歓迎会にはかつてのライバル、水原茂、松木謙治郎、藤村富美男、川上哲治、千葉茂らそうそうたるメンバーが顔をそろえた。
投手とのコミュニケーション能力が問われる捕手というポジションに、A・マルティネスは外国人として抜てきされた。与田監督以下首脳陣も、言葉のハンディなど百も承知での起用に違いない。懸命なプレーと誠実な人柄で、周りの評価も高いと聞く。今から38年後といえば、21世紀も半ばを過ぎた2058年。先輩ハリスのように、日本の人々に長く愛される捕手になってほしい。【記録室 高野勲】