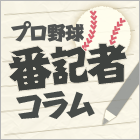「倉商で、東京五輪の観戦を募集したの。3年生で見に行きたい人が対象。バレーか、サッカーか」。1964年(昭39)。当時17歳の青年星野仙一は「東京に行ったことがないから」と母の敏子さんに頼み込んだ。
「行きたい人があまりにも多くてさ。落選。だから新幹線に初めて乗ったのは明大の受験で、新大阪から。あれ…音もせずに走ってるってな。『やるぞ~』って、元気があふれていた。我々、団塊の世代の、前の世代だ。忘れてるんだよ。日本という国が経済大国になったのは、団塊の前の世代が頑張ったからだ」
44年の時を経て、北京五輪で辛酸をなめた星野監督。楽天の監督に就任した当初は競技から外れていたし、特に話題にすることもなかった。
4年前の7月、電話で「アメリカの道路事情と治安」というたわいもない雑談が終わり、ふと尋ねた。「そう言えば野球、五輪復帰が決まりましたね」。
まじめな低音に変わって、一気に語った。
「尽力したすべての関係者に『ありがとうございます』と感謝したい。東京五輪で復帰は最高のタイミング。20年の先も野球が国民に愛され続けるために、球界全体をビルドアップする好機としなくてはいけない。五輪の野球競技は、アマチュアに返すべきだと考えている。『子どもたちのあこがれを取り戻す』という大局観が大切だ。少年野球チームの急激な減少率からいって、野球人口の減少は少子化だけが理由ではない。五輪はあこがれの象徴にふさわしい」
急に…黙っていると「これは新聞にしっかりと載せてくれ。オレの考えだ」と添えた。
1年後。「稲葉監督に決まりました。何かありますか」と振ると、今度は小さな声で「もういいんだ」とつぶやいた。発言に対する責任を考えていたのだと、今は分かる。時間が足りなかった。
2020年。星野さんと五輪について、やりとりをつづってみた。1月4日は思い出す日。合掌。【宮下敬至】