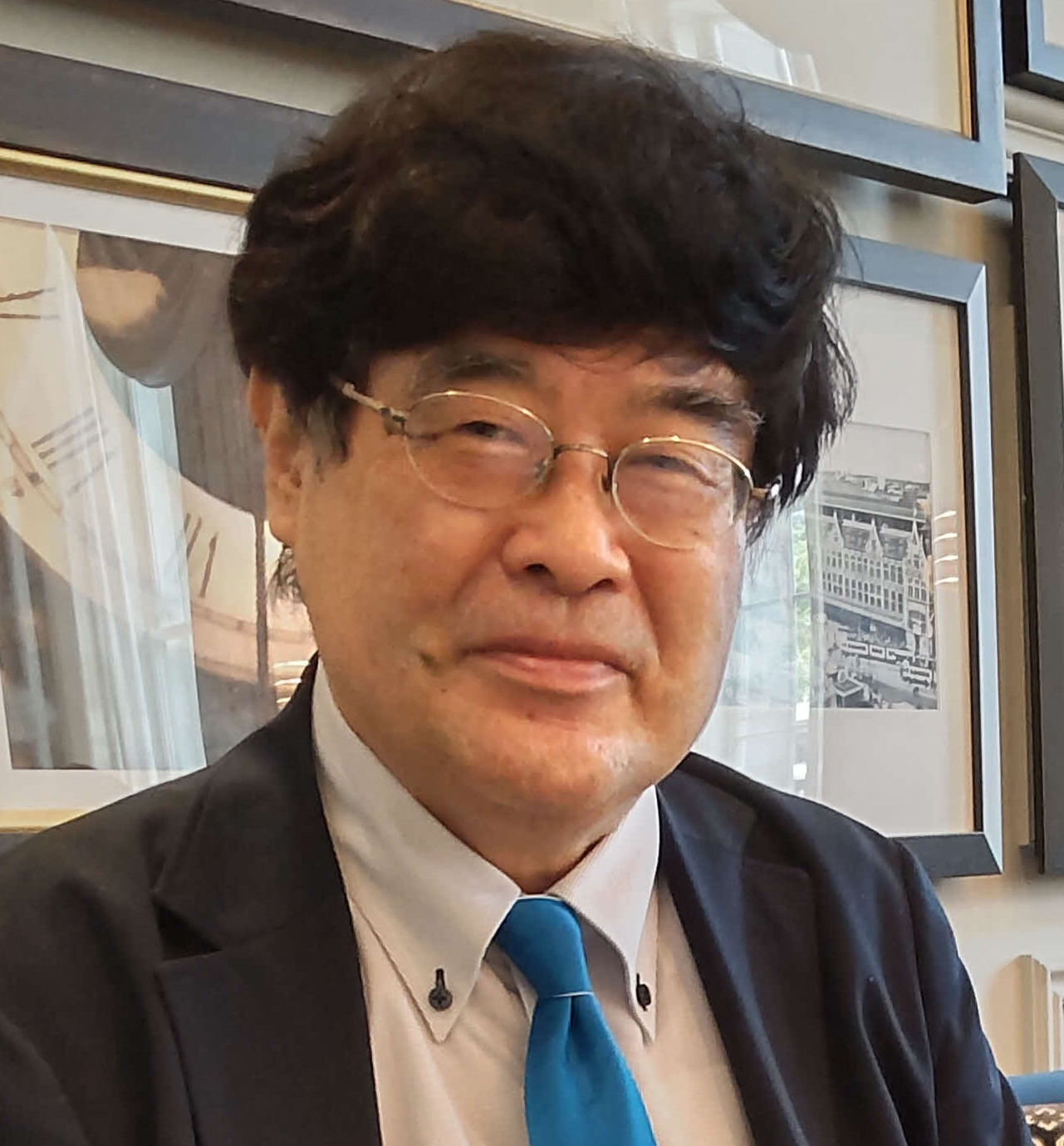【ブッチャーの真実〈5〉】ディスコにもうどん店にも凶器持参、心優しい悪役
日本プロレス史上最も有名な外国人レスラーが、『黒い呪術師』アブドーラ・ザ・ブッチャー(81)だ。希代のヒール(悪党)レスラーでありながら、なぜか絶大な人気を誇った。いったいブッチャーとは何者であったのか。関係者の証言をもとにたどる。連載最後となる第5回は「愛された理由」。
プロレス
悲鳴が大歓声に変わった80年代
1987年(昭62)11月に開幕した『世界最強タッグ決定リーグ戦』で、アブドーラ・ザ・ブッチャーはTNTとタッグを組んで、約6年半ぶりに全日本プロレスのリングに復帰した。
どこの会場も盛況で、彼が登場すると大歓声と“ブッチャーコール”に包まれた。その商品価値は依然として高かった。
ただ70年代の“ブッチャー人気”とは明らかに質が違っていた。
77年12月の『世界オープンタッグ選手権』で、初めて凶器にフォークを使ってテリー・ファンクの右肩を突き刺し、会場は怒号と悲鳴に包まれた。ブッチャーは“悪の権化”だった。会場全体を戦場とする暴走ファイトに観客は逃げまどった。当時の人気は恐怖の裏返し、『怖いもの見たさ』的なものが根底にあった。
あれから10年。ファンにとってブッチャーは『愛すべきヒール』になっていた。怒号と悲鳴は、大歓声と“ブッチャーコール”に変わっていた。リングの上でこっそりと凶器のフォークを取り出すと「待ってました!」のヤジが飛んだ。
試合後、ブッチャーが控室に戻る際には、色紙を手にした子どもたちが花道に群がった。サインをもらうためではない。魚拓(ぎょたく)のように額から流れる血を、ペタンと色紙につけるためだ。ブッチャーは決して振り払おうとはしなかった。
元東京スポーツ記者の柴田惣一氏(64=現プロレス解説者)は、その理由を直接本人に聞いていた。
「流血する額に色紙を付けられて何で嫌がらないのかと聞いたら“オレがサインをするわけにはいかないだろう。だからせめてファンにオレの血を色紙に付けてもらい、喜んでくれればそれでいいんだ”と。ヒール(悪役)はサインなんかしなかった時代。彼の精いっぱいのファンサービスだったんです」。
シンやザ・シークがヒール貫く一方で
当時、ヒールのレスラーの中には、リング上の自分のイメージを保つために、リング外でもヒールに徹する選手もいた。彼らはそれが“プロフェッショナル”だと考えていた。
代表格が新日本プロレスでアントニオ猪木と幾多の名勝負を繰り広げた“インドの狂虎”と呼ばれたタイガー・ジェット・シン。取材記者を蹴散らし、観客に危害を加えることもあった。
全日本時代にシンの信じられない光景を、グレート小鹿(80)は目撃している。
「北海道の稚内での興行で、会場にパイプイスがなくて、お客さんは青いシートの上に座って観戦していた。シンの試合で場外乱闘になって、客はみんな逃げたんだけど、足が悪くて動けないおじいちゃんが一人だけ残された。するとシンがそのおじいちゃんの顔をバーンと蹴ったんだ。目が腫れてねえ。プロなら絶対にやってはいけないことだ。オレたちがお土産を渡して謝ったよ」。
同じヒールでも、ブッチャーはリングの中と外を、きっちりと使い分けていた。柴田氏はシンと対照的なこんなエピソードを記憶していた。
「試合前の乱闘で、ブッチャーが誤って花束嬢に当たってしまったんです。そしたら試合後“ごめんね。そんなつもりじゃなかったんだ”と彼女に直接謝罪にきたと聞きました」。
メディアの取材にも協力的で、試合を終えると記者たちとも陽気に接した。
ブッチャーを初来日から取材し、個人的にも親しかった元東京スポーツ記者だった門馬忠雄氏(84=現プロレス評論家)は、締め切り間際の夜中に突然、ブッチャーが会社に訪ねてきて焦ったという。
「会社でゴルフの米ツアーの速報記事を書いていたら、受付から“ブッチャーさんがいらっしゃいました”と連絡がきてね。当時、会社は築地で、彼は同じヒールレスラーで“ハワイの巨象”と呼ばれていたキング・カーチス・イヤウケアと2人で銀座のホテルから歩いてきた。写真をくれと。午後11時の締め切りが迫っていて、1分でも惜しい時間だったから泣きたくなったよ。だから“ジャスト・モーメント”って言ってね。2人は仕事終わるまでじっと待ってたよ。それにしても、おばけみたいな2人が夜中に突然やってきて、受付の人もびっくりしたと思うよ」。

首藤正徳Masanori Syuto
1988年入社。ボクシング、プロレス、夏冬五輪、テニス、F1、サッカーなど幅広いスポーツを取材。有森裕子、高橋尚子、岡田武史、フィリップ・トルシエらを番記者として担当。
五輪は1992年アルベールビル冬季大会、1996年アトランタ大会を現地取材。
2008年北京大会、2012年ロンドン大会は統括デスク。
サッカーは現場キャップとして1998年W杯フランス大会、2002年同日韓大会を取材。
東京五輪・パラリンピックでは担当委員。
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈15〉最終回~復活1回KO、そして最強神話との惜別~
鉄人が砕け散った日〈15〉最終回~復活1回KO、そして最強神話との惜別~ プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈14〉KO負け前に勝っていた?誤審?再戦?前代未聞の勝敗保留
鉄人が砕け散った日〈14〉KO負け前に勝っていた?誤審?再戦?前代未聞の勝敗保留 プロボクシング4団体統一世界スーパーバ…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈13〉遅すぎた大砲と、最後にすがったもの
鉄人が砕け散った日〈13〉遅すぎた大砲と、最後にすがったもの プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈12〉さび付いていたKOマシン、火を吹いたダグラスの秘密兵器
鉄人が砕け散った日〈12〉さび付いていたKOマシン、火を吹いたダグラスの秘密兵器 プロボクシング4団体統一世界スーパーバ…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈11〉筋肉の落ちたふくらはぎ、5万1600人に露呈した異変
鉄人が砕け散った日〈11〉筋肉の落ちたふくらはぎ、5万1600人に露呈した異変 プロボクシング4団体統一世界スーパーバン…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈10〉最強ライバルに、トランプまで…決戦前から注目は東京D後
鉄人が砕け散った日〈10〉最強ライバルに、トランプまで…決戦前から注目は東京D後 プロボクシング4団体統一世界スーパーバ…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈9〉大遅刻の記者会見、そして挑発と反抗…荒廃したの心の闇
鉄人が砕け散った日〈9〉大遅刻の記者会見、そして挑発と反抗…荒廃したの心の闇 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタ…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈8〉深刻なホームシックと、無敵王者がすがった睡眠療法
鉄人が砕け散った日〈8〉深刻なホームシックと、無敵王者がすがった睡眠療法 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈7〉なぜ伏兵ダグラスが挑戦者に抜てきされたのか
鉄人が砕け散った日〈7〉なぜ伏兵ダグラスが挑戦者に抜てきされたのか プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈6〉屈辱の一般公開スパーリングと、羽目を外したタイソン
鉄人が砕け散った日〈6〉屈辱の一般公開スパーリングと、羽目を外したタイソン プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈5〉細くなっていた、史上最も太い首
鉄人が砕け散った日〈5〉細くなっていた、史上最も太い首 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥(3…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈4〉スイートルームで見せた、仮面の下の素顔と孤独
鉄人が砕け散った日〈4〉スイートルームで見せた、仮面の下の素顔と孤独 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈3〉〝タイソンが倒された〟世界に打電された衝撃ニュース
鉄人が砕け散った日〈3〉〝タイソンが倒された〟世界に打電された衝撃ニュース プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈2〉タイソン怒りの練習中断「狂いが生じたKOマシン」
鉄人が砕け散った日〈2〉タイソン怒りの練習中断「狂いが生じたKOマシン」 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級…

首藤正徳
-
 ボクシング
ボクシング鉄人が砕け散った日〈1〉井上尚弥の34年前、タイソン東京D防衛戦を巡る新連載
鉄人が砕け散った日〈1〉井上尚弥の34年前、タイソン東京D防衛戦を巡る新連載 プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタ…

首藤正徳