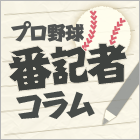テレビのニュース番組が、店の前の公衆電話を守り続ける神戸市の喫茶店の女性店主を取り上げていた。携帯電話の普及におされ、今は使用頻度が激減した公衆電話。緑の機械を大事に守る姿に、27年前の1月17日がよみがえった。
阪神・淡路大震災が起きた1995年のその日。阪神担当だった私は、阪神和田豊、仲田幸司らの自主トレ取材で大阪から滋賀・大津市に行く予定だった。だが、大震災で交通網は遮断され、身動きが取れなくなった。取材に行けないことを和田らに伝えようと、自宅の電話の受話器を取り上げたが使えなくなっていた。どうしようと頭を抱えるうちに、近所にある緑の公衆電話を思い出した。テレホンカードを握りしめて走っていくと、電話の前に行列ができていた。よかった、使える…と胸をなで下ろし、順番を待って和田や仲田らが宿泊するホテルに電話した。
フロントに電話の趣旨を伝えると、和田の部屋につないでくれた。すると驚いたことに、和田が待ちかねたように電話口に出てきた。「家の電話がつながらなくて、嫁さんと連絡が取れないんだ。大阪からだと、なんとかならないかな」。切羽詰まった様子で話し「ちょっと待って」と仲田に代わった。「マイクです。そちらも大変でしょうが、お願いします」。どちらの声からも、被災地の兵庫県にいる家族を案じる思いが伝わってきた。
緑の公衆電話に並び直して和田家、仲田家に電話したが、つながらない。滋賀に取材に行けないなら、とりあえず甲子園に行こうとタクシーをつかまえた。車中で、そもそも甲子園は無事なのか? でも、ニュースにも出てこなかったし、と思いを巡らせるうち、到着。甲子園は、あるべき場所に建っていた。あちこちに深い傷を負ったことはのちにわかったが、一見変わらぬ姿でそこにあった。
プレスルームの電話でかけてみると、和田家にも仲田家にもつながった。夫人に涙声でお礼を言われ、選手たちに家族の無事を伝え、ほっとして座り込んでいたら、プレスルームの電話が鳴った。大阪・豊中市の本社にいるトラ番キャップからだった。「会社の電話が使えんから、1階の公衆電話からかけてるんや。原稿の指示はこっちから連絡するから、気をつけて頑張ってくれ」とせわしなく電話を切られた。
何度も余震が来て、甲子園のプレスルームは揺れた。テレビは、想像するだけで胸が苦しくなる痛ましいニュースを伝え続けていた。亡くなった方、行方不明者の人数が、どんどん増えていく。会社の公衆電話の前では、日刊スポーツの社員たちが順番待ちしていたという。
「ありがとう。助かったよ」。電話口で声を震わせていた和田は、阪神監督を経て、今では阪神テクニカルアドバイザー(TA)。日刊スポーツは豊中市から大阪市北区に引っ越した。いろんなものが変わったが、27年たった今も1月17日がよみがえる。緑の公衆電話はあの日、日常をつなぎとめてくれる大事なツールだった。【遊軍=堀まどか】