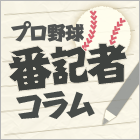長年、取材現場に出ていると避けられないものがある。感覚のマヒだ。かつて感動できたことに、不感になってしまう。初めて見たもの、感じたことが年々、更新され、ハードルが上がっていく。
そんな鈍りつつある感性を打ち砕かれたのは、3年前だった。19年3月31日。センバツ大会は準々決勝真っ盛りだったが、向かったのは栃木県内の練習試合。当時、評論家だったサブロー氏(大村三郎、現楽天スカウティングアドバイザー)と、大船渡の剛腕を見に行った。
初回の2、3球で悟った。今まで見てきた、高校生投手とは比類できない、と。長くない取材歴でも、ダルビッシュ有や岸孝之の高校時代を目の当たりにする運に恵まれた。その経験の領域を、はるか上を行った。
隣に座っていたサブロー氏も数球で「これは、すげぇな…」と、しばらくは言葉が出なかった。ある球団のスカウトも「高校生の中に白鵬がいた」と、酔いしれていた。高評価のコメントを残すことがスカウトの仕事の1つでもあり、記者も割り増しの称賛と受け止めることが多い。だがこの日ばかりは、恍惚(こうこつ)の表情から出た言葉は額面以上の衝撃だったことを感じた。
翌年、プロ入りした怪物のブルペンを真後ろから見た先輩記者が「何かをやってみよう、何かを変えてみよう、できなかったことに挑戦してみよう、そういう気持ちにさせるエネルギーが発散されている。御利益がありそうな、そんなボールだった」とコラムにつづった。
何を大げさな。そう思う読者もいたかもしれない。だが、あの練習試合の衝撃を肌で感じた私も、激しく同意する。
近年、コロナ禍で現場に足を運べる機会、距離感は制限されている。一方でリモートで得られる情報量も確実に充実度が増している。それでも現場でしか受けられない感動がある。当時、17歳だった佐々木朗希が教えてくれた。【遊軍担当=広重竜太郎】