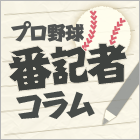200球を超えないと、見えない境地がある。
西武野上亮磨投手(29)はそう言って、無人のブルペンに入っていった。
18日、西武1軍のキャンプ地、宮崎・南郷中央公園。メイン球場で紅白戦が行われている最中とあって、半室内になっているブルペン周辺にはまったく人けがなかった。
そこに、投球がミットを鳴らす捕球音が、メトロノームのように鳴り響き始めた。やがてわずかに音の高さが変わり出す。試合同様、変化球も交えた配球をしているからだ。
30分を過ぎ、1時間がたっても、音はやまない。投球数も200球、そして300球を超えた。
約2時間後。野上はようやくブルペンを後にした。投げ込んだ数、386球。紅白戦に先発しての8球、その直前のウオームアップ時の38球も合わせると、1日に432球を投じたことになった。
◇ ◇
この球数は自己最多だが、毎年この時期に1度は200球以上の投げ込みを行うのが、野上流の調整だ。
試合さながらに、配球をしていることもある。100球あたりから、腕を振るのがきつくなってくる。
それでも投げ続けると、ふと「壁」を超える瞬間がある。
「プロ入り直後、キャンプで牧田さんと一緒にブルペンに入ったら、なんとなく先に投げ終えたら負けみたいな雰囲気になった。それでムキになって投げ続けていたら、200球を超えたあたりから、ふっと楽になったんです」
苦境でもがくうちに、身体はムダのないフォームを自然と探し当てる。
加えて今年は自主トレで、トレーナーから効率的な身体の動かし方を、徹底的に教わってきた。それもあり、今年はすんなりと「領域」に入ることができた。そう、満足げにうなずく。
細身の身体に宿る力を、いかに効率的にボールに伝えるか。投球動作のムダをそぎ落とし、研ぎ澄ませる。1人こもったブルペンで、何度も捕球音を響かせる様は、工房でつちを振るう刀匠のようでもある。
なぜ、動作をとことん磨くのか。野上は「シーズンになれば、必ず『この1球』という場面が来る」と遠くをみつめて言った。
試合の流れ、さらにはシーズンの行方を決める1球。その場面はおそらく、体力的にも精神的にも極限の状態で訪れる。
そこでこそ、最高のボールを投じたい。自己最多の432球も、1年に1度の「1球」につなげるプロセスだった。
◇ ◇
「優勝したいんです」
高知・春野に移動しての2次キャンプ。ブルペンから出てきた野上が、ポツリと言った。
投球練習のやり方は「432球」を境に変わった。セットポジションを取り、仮想する走者を目線でけん制するシミュレーションを行いつつ、1球、1球と時間をかけて投じる。
変化球の割合も増えた。フォームを研ぎ澄ませる段階から、実戦を意識した段階に進んだ証しだ。
ロッカールームに引き揚げる道すがら。苦笑いしながら吐露する。「僕はプロでも優勝してないですし、高校でも社会人でも準優勝止まりなんですよね」。
1球に泣いてきた。
今も思い出す。神村学園高3年夏の鹿児島大会決勝、樟南高戦。野上がエースとして引っ張るチームは、8回終了時点で4-1とリードしていた。
センバツでは準優勝。日本一にあと1歩届かなかった。そのリベンジの舞台まで、あとアウト3つまで迫っていた。しかし9回表、野上は無死満塁のピンチを迎えた。
打席には、後に阪神でプレーする前田大和。カウント1-1からの3球目、スライダーが甘く入った。
打たれた瞬間、野上は打球の行方を見るよりも先に、天を仰いだ。左中間を破る、走者一掃の三塁打。
「ヒジが痛くて、ギリギリで投げていた。打たれて気持ちが折れてしまった。戦意喪失。もうどうしようもなかった」。勝ち越しまで許し、逆転負けで野上の高校野球は終わった。
「大事な試合ほど、1球ですべてが変わる。あの後も、1球の重みを何度も思い知らされてきました。そういう場面で、ベストな1球を投げたい。いつもそう思います」
高3の夏は、痛むヒジをかばうので精いっぱいだった。その「1球」は、ベストからは程遠かった。だから思わず、天を仰いだ。
社会人、そしてプロでも1球に泣くたび、自問自答を繰り返してきた。
決して球威がある方ではない。少しでも制球が甘くなれば、痛打される。丁寧なボールの出し入れ、打者との駆け引きなど、苦心のマネジメントで試合を組み立てても、たった1球で水泡に帰することがある。
そのたびに自分に問う。フィジカルコンディションはどうだったか。フォームのバランスはよかったのか。1球の重み、せつなさにさいなまれる。
だからこそ野上は今年も、いずれ来る「1球」を見据え、入念に、丁寧に調整を続ける。
◇ ◇
今季、投手陣の柱だった岸が、楽天に移籍した。
そのこともあって、野上の「1球」についての考え方に、これまでと違う観点が加わった。
「岸さんの穴は、誰か1人で埋められるようなものじゃない。だから今年は雄星を柱に、投手陣がチームとしてまとまらないといけない。たとえば3連戦の頭で投げるなら、次に先発する投手の配球の布石になるような投球を意識します」
チームにとって、シーズンを分けるような「1球」は、自分がマウンドにいる時に訪れるとは限らない。
本気で優勝を狙うなら、誰がその「1球」を迎えても、ベストな投球ができないといけない。
今季の野上は、そこまで考えている。
「辻監督もよくおっしゃいますけど、僕も一発勝負の社会人野球育ち。年に1度の大一番に臨む上での、チームのまとまりの大事さは、社会人時代に教わりました。チームのまとまりで勝つ喜びも知っている。プロに入ってからは余裕がなくて、個人的な結果のことしか考えられない時期もあった。でももともと僕は、チームで勝ちたいと思うタイプの人間です」
◇ ◇
26日、春季キャンプを締めくくる練習試合楽天戦。野上は先発を任され、森とバッテリーを組むことになった。
前夜。野上は森に声をかけていた。「お前がキャッチャーなら、半分はスライダーだな」。
実は一昨年も、同じ時期に野上は森とのバッテリーで練習試合に臨んでいた。
その際、あまりにスライダーを多用する森のリードを、野上は注意していた。
単調な配球が打者に読まれやすい、というだけではない。もっと投手と意思疎通をはかり、よい投球を引きだそうとしなければ、チームにとってプラスにならない。そう思ったからだ。
「半分はスライダー」と声をかけたのは、それを踏まえてのことだった。翌朝。チーム全体のウオームアップが始まる直前、森が野上に声をかけた。
「野上さん、今日はどういう配球にしましょうか」
それで十分だった。野上は「お前のサイン通りに投げる」と応じた。
大事なのは、協力してベストの投球を生み出すこと。投手の意見を聞いてきたのは、それが理解できた証だ。
実際、森は昨年と違い、数多くの球種をバランスよく求めてきた。野上の良さを引き出そうと、考えをめぐらせているのが伝わってきた。
捕手としての成長を促している、などとは言わない。野上は「捕手の力も借りて頑張りたいです。投手は孤独ですけど、支えてもらえることもある」とうなずいた。
◇ ◇
投手は孤独。
野上は確かに、そう言った。
先発投手は次の登板機会まで6日間ある。入念に準備ができる反面、仮に負けたとなれば、挽回のチャンスがめぐってくるのは1週間後。次の日にリベンジをはかれる野手とは違う。
6日後の先発に向けて調整するのは自分だけ。その時間を、誰かと分かち合うことはできない。
自分の敗戦からチームの連敗が始まれば、責任も感じる。周囲に「6日間も準備できるのに、何してるんだ」と言われているんじゃないか。そんな疑念にかられることもある。
プロ入り後、野上は何年もロングリリーフや谷間の先発を続け、信頼を勝ち得てようやく先発ローテの一角に入った。
下積みの末に、ようやく得た花形のポジション。しかし実際にそこに立ってみれば、感じるのは晴れがましさよりも孤独さだった。
そんな時、野上の支えになったのは石井一久、岸孝之といった先輩投手の励ましだった。
今年の西武は投手陣の半分以上が1軍キャンプ初参加。若手投手がかつての野上のように先発にのし上がり、一本立ちすることを求められる転換期を迎える。
今度は自分が、孤独と向き合うことになる若い同僚たちを励まし、支えなければならない。
そうやって投手陣がまとまってこそ、優勝争いの中で迎える「1球」の場面で誰がマウンド上にいたとしても、チームとしてのベストピッチができる。
27日。キャンプを終えた野上は、帰京の途についた。チームバスに乗り込む直前。タラップの手前で振り返り、こう言った。
「僕は、みんなで勝ちたい」
【西武担当=塩畑大輔】