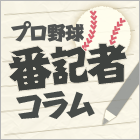ロッテの小島和哉投手(26)が、千葉市内の小学校を訪問した時だった。昨年12月19日、「マリーンズ算数ドリル」の贈呈式に出席した壇上で、小島は小学生に向かって真っ先に言った。
「今日、学校の正門に入ってきた時に『すごく良い学校、すごく良い子どもたちだな』って思いました。みんなが、初めて会ったのに元気にあいさつしてくれた。とても気持ちが良かったです。この学校が好きになりました」
元気なあいさつ。小島投手の言葉を聞いた時、私自身も同投手に好印象を抱いた。同時に、手前みそではあるが、私が大事にしてきたことだっただけに、うれしかった。「おはようございます」「お疲れさまです」「ありがとうございました」。あいさつは当然であるが、しっかり出来ている大人は意外と少ないと感じている。
あいさつの喜び? 重要性? を初めて感じたのは、町内子供会のソフトボールチームで6年生たちに交じって「9番二塁」で試合に出場した小学校3年生の時だった。夏休みの大会で、私の決勝エラーで負けた。当時の心情は定かではないが、その後のバーベキューでも、悔しさ、恥ずかしさなどから、ふてくされてモジモジ…。肉をもらっても、ジュースをもらっても「ありがとう」すら言えなかった。
そんな姿を見て声をかけてくれたのが、ミニスーパーを経営する横山監督だった。「直ちゃん、失敗は誰でもするんだよ。元気に、次はどうしたいか、どうなりたいか、みんなに言ってみよう」。私を元気づけるため? に上級生が1人ずつ目標を叫び、最後は私の番。最初は小さい声でボソボソ…。「もっと、元気に」「もっと大きく」と周りに盛り上げられ、最後は「ホームラン打って勝ちます」。拍手に包まれて気持ち良かった記憶も何となくある。自分自身が落ち込んでいたり、気分が晴れていなくても、相手には関係ない。それ以降は、元気にあいさつすることだけは続けてきたつもりだ。
大学1年の時だった。野球部の練習中、当時の主将に呼ばれた。「後ろ、向いて」。白いユニホームの腰部分に「鎌田」と名前を書いてあったが、その隣に黒の太マジックで「元気」と付け加えられた。「鎌田を試合で使うのは、これもあるから。頼むよ」。先輩たちから「元気クン」と呼ばれる時もあった。
日刊スポーツに入社し、Jリーグのクラブを担当した時も「あいさつ」はコミュニケーションを深める大きな手段だった。毎朝、練習前に元気にあいさつする選手が少なく感じた。「おはようございます」と声をかけても、目をこちらに向けて会釈する程度の選手もいた。それでも、声がけは続けた。ある選手から「元気な記者いるよね、って選手間で話題になっていますよ。自分もチームに元気がないなって思っていたので、ロッカーで朝、大きな声であいさつするようになりました」と言われた。そのシーズン中盤には外国人選手までが元気にあいさつする雰囲気となり、番記者っていいなと思えた瞬間でもあった。
「元気があれば何でも出来る」とは言わないが、カラ元気でも「元気を出せば前を向ける」とは思っている。年が明け、ロッテ担当として本格的に取材する機会が増えた。チーム最年長37歳の荻野貴司外野手は今月7日の公開自主トレで、ZOZOマリンの外野をランニング中にベンチ付近に報道陣が集まっていることを見つけると、わざわざ駆け寄って新年のあいさつに来てくれた。同10日のロッテ浦和球場では、ともに20歳の西川僚祐外野手、山本大斗外野手も、足を止めてしっかり頭を下げ「今年もよろしくお願いします」。寒風が吹く中でも、心は温かくなった。元気をもらった。
今季からのロッテ担当が決まって以降、選手では初めて名刺を手渡した小島投手のひと言から、私も「元気なあいさつ」の初心にかえることが出来た。「よろしくお願いします!」【ロッテ担当 鎌田直秀】