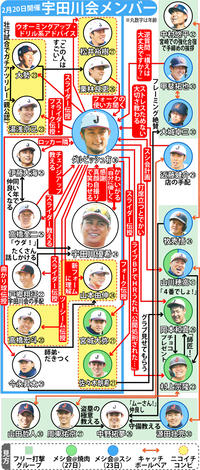16日のWBC準々決勝で日本と対戦するイタリアは、世界有数のサッカー大国。そんな社会で、野球文化はどんな道のりを歩んできたのか。04~06年にイタリアの国内リーグでプレーした経験を持つカメラマン八木虎造さん(48)に、当時の現場の様子を聞いた。今回の選手の多くは大リーグやマイナーリーグ所属。現在の国内リーグも当時とは状況が異なるが、少し前の日常生活の中の野球がかいま見えた。
八木さんは中学まで野球部。カメラマンになり、29歳の04年にイタリアに渡った。同年開催のアテネ五輪を観戦して再びプレーしたくなり、セリエCに所属するシチリア島のチーム「パレルモ」の門をたたいた。リーグのトップはセリエAで、その下にB、Cがあった。
チームは事実上アマチュアで、メンバー約30人のほとんどが本業を持っていた。練習は原則週3日夕方から、試合は土・日曜中心で、1シーズン計約30試合。八木さんはリーグの試合では二塁手や三塁手を務め、打線は1、2番だった。「リーグでは地元育成のためバッテリーなどは外国人はできませんでした。リーグ以外の試合では捕手も務めました」。当時のセリエCのレベルについては「日本の大学生でも勝てるくらいでしたが、その後はかなりレベルアップしていったようです」と振り返る。
普通の野球場もあったが、野球場がないところでは、試合でサッカー場が使われる場合も少なくなかった。「サッカー場ではコーナーにホームベース、ゴール付近に一塁ベースを置くイメージです。選手も野球よりサッカーのほうがうまかった」。試合の入場は無料。観客は親族や友人が多かったという。
どこの学校でも体育の授業で年に1度くらい野球を教えており、八木さんも米国人らと教えに行った。「子どもたちや市民はルールもあまり分からない感じでした。ただ選手たちは非常に真剣で本気でした。ネットでイチローさんらの動画を見たり、情報収集にも一生懸命で、あの熱さは世界レベルでした」。チームからイチローさんと同じ背番号51を与えられていた八木さんは、野球でも欧州では強国の存在感を維持してきた背景を、そう指摘した。【久保勇人】